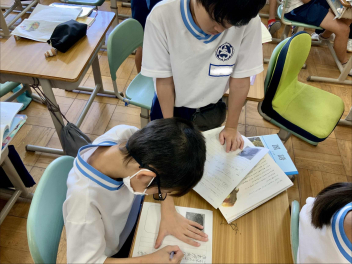9月26日(木)に、4年1組で実習生による国語科の研究授業が行われました。本校で9月8日(月)から実習に励んでいる教育実習生が、これまでの学びの成果を発揮する大切な時間となりました。
今回の授業で取り扱ったのは、4年生の国語科の定番教材、新美南吉作の物語文「ごんぎつね」です。この単元では、「気持ちの変化に着目して読み、感想を書く」ことを目標にしています。特に、登場人物であるごんと兵十の気持ちの変化を、物語の描写や行動と結び付けて深く想像し、読みを深めることを目指しています。
研究授業の本時(単元の5時間目)は、ごんが兵十にしたいたずらを後悔し、「つぐない」を始めた場面(場面「3」)に焦点を当てました。
授業の目標は、「ごんがしたつぐないの行動を考えることを通して、ごんの兵十に対する気持ちの変化に気付き、ごんの気持ちを具体的に想像する」ことでした。
先生は、ごんがいたずらをした場面(「1」)と後悔し始めた場面(「2」)でのごんと兵十の気持ちの距離を確認し、本時でごんの気持ちがどう変化していくのかに着目させました。
子供たちは、ごんの行った「ぬすんだいわしを投げこんだ」から「くりをどっさり拾ってそっと置いた」「松たけも2,3本持っていった」というつぐないの行動の変化に着目。
「なぜ、最初は盗んでいたイワシなのに、次は自分で栗を拾って届けたんだろう?」といった先生の発問を通して、つぐないの内容が変わり、その姿勢が強まっていることに気付きました。
その後、ごんの行動の背景にある「兵十喜ぶかな?」「元気出してほしいな」といった気持ちを具体的に想像し、ワークシートに書き込みました。
子供たちは、ごんの具体的な行動や叙述の言葉を手掛かりに、友達との意見交換や先生の発問を通して、自分の考えを深めることができました。ごんと兵十の心の距離を黒板に貼った挿絵の位置で表したり、栗の実物を見せたりといった、視覚的な工夫も、子供たちの読みを深める上で効果的でした。本校では、子供たちが根拠を踏まえて考えるように促す発問や言葉掛けを工夫し、物語を深く読み取り考える楽しさを感じられる授業づくりを推進しています。今回の研究授業は、実習生がこの方針をよく理解し、実践に活かせた、大変学びの多い時間となりました。
今回の授業で取り扱ったのは、4年生の国語科の定番教材、新美南吉作の物語文「ごんぎつね」です。この単元では、「気持ちの変化に着目して読み、感想を書く」ことを目標にしています。特に、登場人物であるごんと兵十の気持ちの変化を、物語の描写や行動と結び付けて深く想像し、読みを深めることを目指しています。
研究授業の本時(単元の5時間目)は、ごんが兵十にしたいたずらを後悔し、「つぐない」を始めた場面(場面「3」)に焦点を当てました。
授業の目標は、「ごんがしたつぐないの行動を考えることを通して、ごんの兵十に対する気持ちの変化に気付き、ごんの気持ちを具体的に想像する」ことでした。
先生は、ごんがいたずらをした場面(「1」)と後悔し始めた場面(「2」)でのごんと兵十の気持ちの距離を確認し、本時でごんの気持ちがどう変化していくのかに着目させました。
子供たちは、ごんの行った「ぬすんだいわしを投げこんだ」から「くりをどっさり拾ってそっと置いた」「松たけも2,3本持っていった」というつぐないの行動の変化に着目。
「なぜ、最初は盗んでいたイワシなのに、次は自分で栗を拾って届けたんだろう?」といった先生の発問を通して、つぐないの内容が変わり、その姿勢が強まっていることに気付きました。
その後、ごんの行動の背景にある「兵十喜ぶかな?」「元気出してほしいな」といった気持ちを具体的に想像し、ワークシートに書き込みました。
子供たちは、ごんの具体的な行動や叙述の言葉を手掛かりに、友達との意見交換や先生の発問を通して、自分の考えを深めることができました。ごんと兵十の心の距離を黒板に貼った挿絵の位置で表したり、栗の実物を見せたりといった、視覚的な工夫も、子供たちの読みを深める上で効果的でした。本校では、子供たちが根拠を踏まえて考えるように促す発問や言葉掛けを工夫し、物語を深く読み取り考える楽しさを感じられる授業づくりを推進しています。今回の研究授業は、実習生がこの方針をよく理解し、実践に活かせた、大変学びの多い時間となりました。